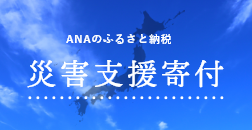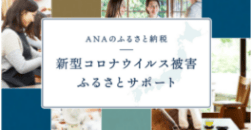返礼品について
京色パステルは選びぬかれた京都の美しい色でつくられた18色セット。
それぞれの色には、京都を感じる色名がつけられており、小さな色の世界に四季折々の京都を感じることができる商品。有害物質不使用で安心してご利用いただけます。
京都文化ベンチャーコンペティション最優秀賞、京都デザイン賞受賞
すぐにお楽しみいただけるように、画用紙をセットにしました。
旅先で出逢った美しい景色を、是非この京色パステルで描いてみてはいかがでしょう?また、お土産やプレゼントとしても大変好評をいただいております。
■使い方
・紙に描いたパステルを指でこすってぼかすと、やわらかな色に
・表面がツルツルした紙には描けませんが、画用紙などなら何でもOK
・描く際には、新聞紙を敷く等、周りを汚さないように
・描き終わった後はキレイに手洗いして汚れを落としてください
■全色名
「黒髪の艶」
小野小町、紫式部など平安女性の優雅で妖艶な美しさを思い浮かべました。
「古都の香」
古都京都を吹く、ちょっとほろ苦い風の色です。
「松ヶ崎菜の花便り」
風に揺れる菜の花―松ヶ崎の夕景は、私の小学生時代の思い出です。
「嵯峨野竹林」
「涼しさを絵にうつしけり嵯峨の竹(芭蕉)」竹の直線的なイメージと葉擦れの音が夏の涼を感じさせます。
「半木の花咲み」
鴨川沿いに紅枝垂桜がつづく「半木の道」。まるで桜の花が、麗らかな春を喜び、ほほ笑んでいるようです。
「京町家の佇まい」
伝統と歴史が醸し出す落ち着いた雰囲気が好きです。
「銀向月台」
銀閣寺の向月台(砂を富士山型に盛ったもの)。月の夜の静けさとはどのような趣でしょうか。
「大原のひだまり」
のんびりぽかぽか。京都大原の光は優しい暖かさで心を包みこみます。
「渡月橋の朝靄」
嵐山渡月橋。早朝、橋は一枚のベールをかぶり、その向こうにはこんもりとした山がうっすらと透けて見えます。
「能の花」
太鼓の音、音との間、笛の響き―「風姿花伝」に書かれた心の動きを表す秘伝が、今も能楽堂には息づいています。
「保津川ソーダ」
トロッコ列車からのぞむ流れ、保津川下りのしぶき、山と岩と水が織り成すのは「ソーダ」!
「早春落ち椿」
深緑の上で映える赤。法然院や地蔵院で出会ったぽとりと落ちてた椿の花。あえて「落ち椿」が美しいとする美の感覚が京らしい。
「平等院の藤波」
風になびく藤を見て昔の人も詠みました。「我が宿の池の藤波咲きにけり 山ほととぎすいつか来鳴かむ(よみびとしらず)」
「祇園囃子」
京都の夏、祇園祭。山鉾の前掛や胴掛が、お囃子や熱気と共に揺れます。絢爛たる祭のイメージです。
「音羽の清み空」
清水寺音羽の滝。清水の舞台から眺める澄みきった空は、私の気持ちを遠いところまで連れて行きます。
「千年紫」
かつて紫は高貴な人しか着ることを許されなかった禁色でした。その深みが似合うのはやはり千年の都、京都かと思います。
「光のどけき日」
「久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ(紀友則)」より。春光の中にはらはらと花が散る、残像の美しい一首をこの色に託しました。
「雨上がりの糺の森」
下鴨神社の境内に広がる原生林、糺の森。古くから「偽りを糺す。の森」と呼ばれる静かな森です。
■自分らしく自由な表現で
パステルには決まった描き方はありません。先に述べたスタンダードな使い方以外にも、様々な使い方がされています。たとえば、
・紙に描いたパステルを、水で濡らした筆で伸ばすと水彩風に
・削ったパステルを紙の上で伸ばして、やわらかい風合いに
・ステンシルと併用して、色々な模様を
・紙の凹凸や色を変えて、違いを表現
1人1人自分らしい、自由な表現でお楽しみください。
■ひとつひとつ、ハンドメイド
ここにしかない色、にっぽんの色
持ち運びやすく、色を選び取るだけで描けるパステルは写生を重視する画家や色彩表現に重きをおく画家たちにに支持されてきました。 今も、ゴンドラパステルの確かな品質はプロにもアマチュアにも大きな信頼を得、日本で唯一のソフトパステル専門メーカとして多くの方々に愛されております。高品質、有害物質不使用、職人による手づくりを続けています。
■王冠化学工業所■
ある画家の「日本の風景を描ける色のパステルを作ってほしい」という要望から、われわれは日本初の国産ソフトパステルメーカーとして、1919年に京都東山の地で誕生しました。それから100年以上に渡り、「本物の色」「日本の色」を提供し多くのアーティストに愛されてきました。現在も国内唯一のソフトパステル専門メーカーとして、積み重ねた技術と創業時からの手作りの多い手法で、1本1本丁寧に製造しています。ものづくりの手法や文化を大切に守りながら、現代に合った魅力ある商品作りに挑戦し、ユーザーの心に響くものづくりを目指しています。
- 返礼品レビュー
- 自治体への応援メッセージ